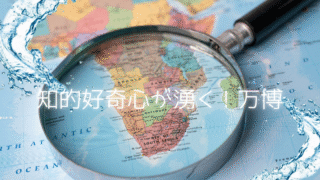夫婦育休の半年間【夫が長期間の育休を取って良かったこと】
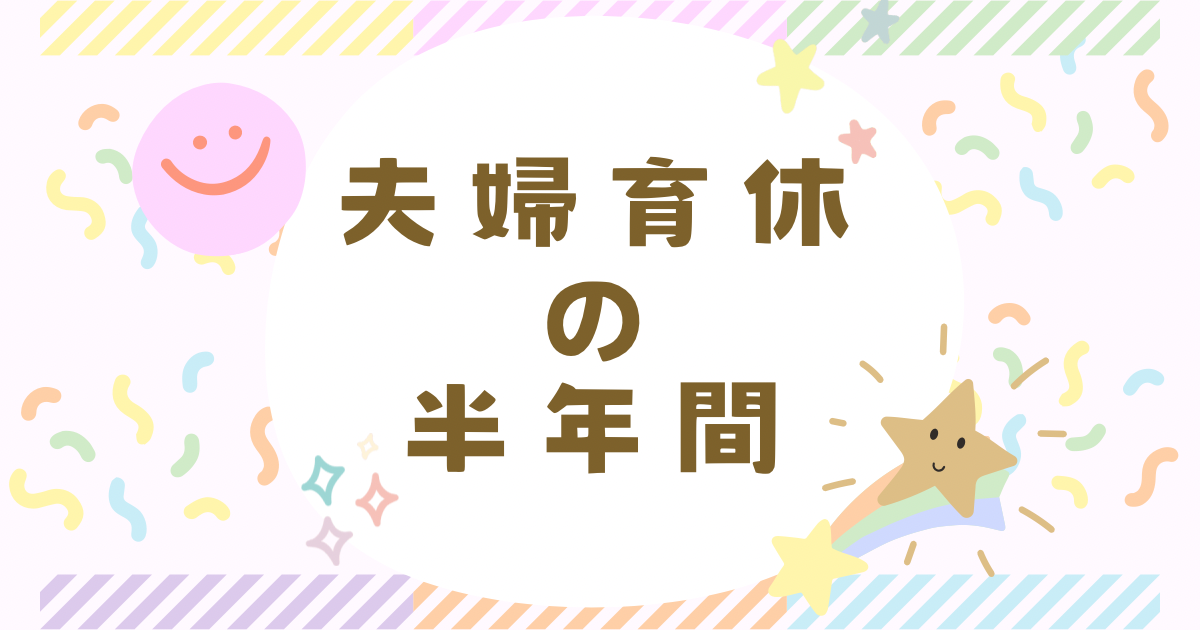
今回次女出産にあたり、夫が育休を半年超取得することができました。
それにより、私が里帰りから戻ってから保育園入園までの間夫婦でこどもをみていました。
これは振り返って本当に良かったと感じています。
夫が長期間の育休を取り、夫婦で育休期間を過ごしたうえで感じたことなどを書いていきます。
これから育休を取られる方の参考になれば幸いです。
わが家の育休取得の話
夫はもともと仕事柄育休が取りやすい環境にいました。
とはいえ積極的に取りたいと言わなければ、夫側の長期間の育休は取れないものです。
私はかねてより夫に、
「3ヶ月くらい育休を取って欲しいが、先方との交渉のために先に6ヶ月欲しいと伝えて。そのときに6ヶ月は長いけど3ヶ月ならまぁ、という感じで調整して取得できるかもしれない。6ヶ月そのとおりいけたら御の字。」
と伝えていました。
先に取得できそうなMaxを提示して欲しいということですね。
すると運よく、当時の仕事内容の兼ね合いや職場や上司の理解もあり、言ったそのとおりの6ヶ月ほどが取得できました。
さらに私が出産後退院してから家に戻るまでの期間のいくらかも休みを取り、上の子の保育園の送り迎え等をしてもらっていたので、実際はもっと長期間です。
なかなか夫側にこのくらいの期間を取らせてくれる職場はそうないでしょう。
感謝です。
上の子のときも育休をとってもらいました。
その時の上司がシングルファーザーだったので育児の苦労を分かってくださっていて、むしろ推奨という感じ。
ただ繁忙期があった兼ね合いで、今回のように長くはありませんでした。
夫側の育休はできるだけたくさん!
夫側の育休は取れるだけ取りましょう。
数日間だけ取ったとて。です。
「◯◯体験」しかり、ちょっとかじっただけでは苦労はわかりません。
当事者意識も育ちません。
例えばプレパパ講習などである「妊婦体験」。
男性がおもりを付けて「妊婦体験」をしても、「そんなしんどくないのでは?」と思われただけという話がありますよね。妻側からしたらブチギレ案件です。
実際は、おもりとは違って内蔵から重くて、寝返りさえも辛いものです。それが数ヶ月という長期間。
体調不良や赤ちゃんに対する気遣いや不安などもあり、お酒など口にできないものも増え薬も満足に服用できません。ほんと、代わってみろ!といいたくなります。
育児も同様です。
四六時中赤ちゃんをみるということには、1日2日などではなくしばらくやってみないとわからないしんどさというのがあるものです。
そして人生のうち、
「生まれて間もない可愛い我が子をじっくり見守れる期間」
「パートナー(妻)からの信頼ポイントを大量に得るチャンス期間」
なんてそうそうありません。
私の母と祖母は育児が終わってウン十年ですが、夫が子育てをやってなかった云々と今でも言ったりしますからね。
この頃の姿勢言動行動は、良くても悪くてもしっかり覚えてます。
「ふたりいて暇にならないか?」
なりません。
でももしなったら、やったーでいいんです。
育休中手のかからない赤ちゃんだったなーと、貴重な家族の時間を楽しんだらいいと思います。
けれど、今ふたりだからいいけどこれひとりだったら…とゾッとする割合のほうが多いと思います。
そして夫側は、産後間もない母体を労ってあげてください。
産後の肥立ちが良くても、体は無理をしています。
産後ハイになってたり気が張ってたりして元気そうに見えることもありますが、母体にしかできない妊娠出産母乳以外は夫側にたくさん比重を寄せてください。
ワンオペとふたり以上では全然負担とその感じ方が違います。
余裕をもって育児に臨んで、家族の時間を大切にできたらいいですよね。
そしてがっつり育休が取れれば、その職場の男性は後に続きやすくなるんです。
のちのちの後輩のために、いい前例を作りましょう!
夫婦での長期育休のデメリット
概ね夫婦ととに育休をとることにデメリットは感じませんでしたが、強いていえばということを。
キャリアに対する不安
育児休業で長期で休むことがキャリアに響くかもしれない。
男性だとこうした考えが強いかもしれません。
もしくは、男性の育児休業の取得が進んでいない会社だったり、育児休業をとることを良しとしないあるいは不要と考える職場風土があったりすると、出世レースから外れるという恐れもあるかもしれません。
しかし、可能であれば少しでも、そしてできるだけ長く育児休業をとってほしいと願います。
赤ちゃんとしっかり向き合い成長を見守ることは、そうしたことをさしひいても尊い時間だと思っているからです。
生まれてすぐの赤ちゃんは、1日1日変わっていくのです。
これからの人生で滅多とない貴重な時間を大切にして欲しいのです。
それから、昔に比べると育児休業への社会や会社の見方が変わってきています。
ぜひそうした風土がない職場でも勇気を出して、先駆者・前例となってください。
多くのひとが当然のように育休を長期間取得する流れができれば、それが普通になれば、出世には影響しなくなるでしょう。
そして、やっぱりどうしても育児休業はできないという男性は、有給や時間給をこまめにとったり、せめて残業がないように努めたりして、なるべく家庭にいる時間を増やしましょう。
あるいは家事代行サービスを利用するなど、家庭でのワンオペにおけるしんどさを軽減するようにしてください。
金銭面
これが結構ネックに感じるのではないでしょうか。
育休中は給与が無しになり、代わりに前年度の収入のおよそ3分の2が育児休業給付金として取得できます(6ヶ月を超えると2分の1)。
夫婦ともにその形になればしんどくなりそうですよね。
ただ、税金の免除などがあるため、手取りとしてガクンと下がったりはしません。
給付は2ヶ月に1回になるので、その点は注意です。
(育児休業給付なので、初回の給付金入金は産休が明けてからの算定となり、出産からおよそ4ヶ月後です。その間は貯蓄でまかなうことになります。)
わが家の場合、仕事があるときは昼食はそれぞれ外食しており、その費用をお小遣いに含めていたので、それをなしにしました。
赤ちゃんがほんとに小さいときは遠出もできないのでレジャー費は少ないですし、人手があるので時間がないから惣菜を買うというシーンも減りました。
そのため、赤ちゃんがいることによる必要経費以外それほどたくさんのお金は使いませんでした。
ただ、育休をとるとらないにかかわらず、赤ちゃん用品や保育園入園前の準備にはお金がかかります。
わが家では長女や友人からもらったおさがりもありいくらか余裕がありましたが、このあたりは注意しましょう。
私の育休中はまだでしたが、2025年4月から、この給付金の制度の改正が行われました。
一定の条件がありますが、活用すれば手取りベースで育児休業前と同じくらいの給付金を得ることが可能になります。
それであればここはあまりデメリットになりませんね。
24時間夫婦
仕事をせず家事育児をずーっとする夫婦。
いいことですが、24時間一緒なのが何ヶ月もとなると息がつまるときもあります。
コロナ禍で夫婦ともに在宅勤務をした経験がある方はなんとなくわかっていただけるのではないでしょうか。
ひとりだとなんなりと適当にするお昼ごはんも、相手がいるともうちょっとちゃんとしないといけないかな、と思ってしまったり。
家事育児の分担に偏りが発生する。
家事育児への考え方が違う。
趣味などに割く時間の捉え方が合わない。
そうしたことで喧嘩もあるかもしれません。
予め話し合いができているといいですね。
ざっくりとした分担を決めておくのも手です。
「空いてるほう、気付いたほうがやる」ばかりでは、ひとりの負担が重くなる可能性があります。
そして折角ワンオペでなく人手があるので、ひとり時間をお互いに取れるようにするのが円満のコツです。
近所のカフェでひとりでコーヒーをゆっくり飲む時間でもあれば、ストレスは結構軽減されます。
赤ちゃんが寝ていて育児に追われていない隙間時間は、定年退職後こんな感じかなーという実感が持てます。
そのときに何か課題があれば、将来のために改善できるといいですね。
夫婦長期育休のメリット
次にメリットの方を。
マンパワーが増える
とにかくこれです。
片方が赤ちゃんの相手、もう片方が家事という分担ができるのはとても大きいメリットです。
「いただきます」を言った瞬間に泣く赤ちゃん、なんて日常茶飯事ですが、ふたりいたら交代で食べれるんです。
何か用事があっても「赤ちゃんいるから…」とワンオペだとできないことでも、もう片方に赤ちゃんを任せられるんです。
漫画とかの「俺があいつの気をひいている間に……!」ができるというわけです。
ワンオペで赤ちゃんとおでかけすると、荷物も多いし段取りが必要だし疲れます。
ですがふたりだと、荷物をもつひとと赤ちゃんをもつひとで分担でき、片方がトイレに行く間はもう一方が赤ちゃんをみておくということができます。
最近は出先の施設でも、おむつ替え台が男女どちらも使用できるところが増えたので便利になりました。
複数人で見られるなら、ちょっと距離がある遊び場でも行くハードルがさがります。
孤独感がなくなる
ワンオペでずっと赤ちゃんといると、孤独感が深まります。
賽の河原のごとく、終わりが来ない家事育児。
それをみて評価してくれるひとがいません。
たまに児童館に連れて行っても「◯◯ちゃんのお母さん」と呼ばれ、個人としての存在が薄くなります。
ことばの通じない赤ちゃんだけを相手していると、話し相手がほしくなります。
それが、夫婦でいることで孤独感が解消されます。
話す相手がいて、当事者同士として育児のことを共有して愚痴も言い合える。
これは精神的にとてもプラスになります。
上の子の育休中、これが個人的に辛かったですね。
私が早く職場復帰をしたくなったのはこれが結構大きかった。
母としてでなく私個人として呼ばれ求められることがしたいなと感じたんです。
それから、夫が仕事から帰宅して喋りたくてもこちらからの話題があまりないうえに、夫からしたら自分だって喋りたいし育児の愚痴ばっかり聞くのはしんどいですよね。
赤ちゃんの情報を自然と共有できる
赤ちゃんが今どういうことができて、何に興味を持っているのか。
離乳食はどこまで進んでいて、アレルギーはないか。
ワクチン接種をいつ行うか。
こうした情報が、一緒に育休をとり一緒に子育てをしていると自然と共有できます。
自然と、というのは重要です。
カレンダーでワクチン接種のことを書いて相手がそれを認識しても、「この子は⚪︎時に寝ることが多いから事前に⚪︎⚪︎をしておかないといけない」「前日までに問診票を書いておこう」といったこととその手間や大変さを共有しているかどうかで大きく違います。
情報が一方に偏っていると、共有に労力を割くのが億劫でもういいやとなってしまい結果的に「任せられない」「自分がやるのが早い」に陥りがち。
人ごと感がなく一緒にやる仲間あるいは同志としてやっていけるなら心強いですね。
赤ちゃんの成長を一緒に喜べる
赤ちゃんの生まれて数日の間の小動物のような声。
甘いにおい。
羽二重餅のようなほっぺ。
自分のおならにびっくりするようす。
必死でへたくそな授乳。
初めての寝返り。
初めてのハイハイ。
離乳食。
あまりにも可愛い笑顔。
いかにも人間1年目な拙さ幼さ。
育休で日中ずっといると、わが子のこれらを逃さず知ることができます。
育児の大変さはもちろんあってだからこその夫婦育休をおすすめするわけですが、この「赤ちゃんの可愛いようす」「赤ちゃんが日に日に成長するようす」を一緒に見守り一緒に喜ぶというのがとてもとても大切だと思います。
可愛いわが子の、さらに特に可愛い赤ちゃんの時期。
ほんの数日でできることが増える、目が離せない時期。
社会人生活の中で、他にそんな貴重な数ヶ月があるでしょうか。
仕事の都合や職場環境、色んな状況があるので難しいでしょう。
けれど「無理じゃないかなあ」でおわることなく、ぜひ夫側も積極的に育休を長期間とり、わが子に捧げる数ヶ月間を過ごしてみていただきたいです。
きっと、とってみて良かったと感じるはずです。